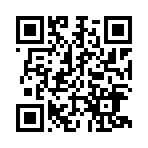無料体験学習
お問合せ:054-201-9801
juku@shunpukan.net
随時受付中です
2013年10月01日
教育の場での罰(体罰について②)

こんにちは。
すっかり秋らしくなりましたが、まだ半袖を着ている春風館の望月です。
さて、前回に引き続き体罰に関するお話しです。
前回は、
「身体的な苦痛や負荷を与えられたとき、それを不当な暴力と感じるか、正当な指導と受け止めるかは内面的な話し」
であり、まあ早い話しが「その時による」ので、
これは体罰だからダメ、ここまではOK、という線引をするのは難しいということについて書きました。
今回は、そもそも「罰」というものは何なのか、教育の場でなぜ必要なのかということについて考えてみたいと思います。
我々は社会で生きる上で、定められたルール(法)に照らし合わせて、
何か悪いことをすれば罰を受けることになっています。
交通違反をすれば「罰金」をとられたり、
詐欺をして捕まれば刑務所に入れられたりするわけです。
会社等の組織内で、「こういう場合は賞与カット」というような罰則を設けている場合もあるでしょう。
本の返却をしなかったので一時的に図書館が利用できなくなる、といったペナルティも、
一種の罰と言えるかも知れません。
こういう「罰」が何のためにあるかと言うと、
残念ながらそういう「罰」を設けておかないとそういうことをやっちゃう人がいるからで、
「罰」を用意しておくことで、犯罪の発生を抑止することが期待されるからでしょう。
では教育の場での「罰」はどうでしょうか?
例えば、宿題をやってこなかった子がげんこつをもらう、
授業中おしゃべりしていた子が廊下に立たされる、
(今は両方NGです。)
期限内に課題を提出しなかったので量を増やされる、
(これはアリです)
こういった「罰」がいろいろあるのだと思います。
授業態度が悪いと内申点が下がる、というのも、とりようによってはある種の「罰」だと考えられるかも知れません。
やはり社会における法律による「罰」と同様に、
「罰」を用意することで、望ましくない行動を抑止するという目的があるように見えますが、
私は、教育の場での罰は、大人に対する罰とはちょっと質が違うものだと考えます。
もちろん抑止という意味合いもありますが、
それに偏重してしまったら、ただ単に「罰が嫌だからやらない」子が育ってしまうわけで、
「罰がなければやってもいい」「罰を受けても平気だったらやってもいい」という話しになってしまいます。
教育の場における「罰」は、もっと何かを「教える」ことが目的でなければなりません。
・自分のした行為が悪いことだと実感させ、分からせるために「罰」を与える。
・世の中にはルールがあり、守らなければならないということを分からせるために「罰」を与える。
・悪いことは悪い、違うことは違う、とはっきりした「けじめ」を教えるために「罰」を与える。
・自分が間違ったことをしてしまった場合、その責任をとることを教えるために「罰」を与える。
などなど。
社会に出た大人がお金を盗んだら犯罪で、捕まれば罰を受けます。
それは悪いと分かっていてやっているのですから、罰を受けるのです。(たまに分かっていない人もいるかも知れませんが)
しかし、成長過程にある子どもは、まだよく分かっていないことがたくさんあります。
教育の場で「罰」を与える場合は、社会のルールや常識、生きるために必要な心の持ち方といったものを教えて理解させることが目的であるはずです。
もっと言えば、罰を与える側は、自分が持っている人間としての正義や哲学といったものを伝える「気概」を有している必要があるのだと思います。
最近の教育現場では、
身体的苦痛を与えるのはNG、
暴言を吐くのはNG、
精神的苦痛を与えるのもNG、
という感じになってきているようですが、
何がNGなのかは
教育現場における「罰」というものの「目的」をふまえて論じるべきだと思います。
体罰に話しを戻せば、
前述したような目的に適うことが明確で、生徒のためになるのであれば、
殴るべきときは殴るべきだと私は考えます。
(ただし、実際には目的に適うかどうかはやってみないと分からず、逆効果になる危険性もあるので、
多くの場合教える側は内心の迷いや恐怖と戦いながら勇気をもって拳を振るうことになります。
でも、教える側というものは常にそういうものです)
悪いことをしようが怠けようが、先生は口ではいろいろ言ってもそれ以上は何もできない。
オレは何を言われても気にしないし、先生の言うことなんか聞かなくても平気だ、
と居直っている生徒もいるようです。
しかしそういう生徒は、誰かがいろんなリスクを背負ってでも、
自分を本気で殴ってくれるのを待ち望んでいるように見えることもあります。
繰り返しになりますが、教育の場での「罰」は子どものために、「教える」ために行われるものでなければなりません。
「こういう罰はNG、こういう罰はOK」
と表面的な規制を強めていくことで、
子どもにとって必要な「罰」が与えられず、
教育上はあまり意味がなく、逆効果になるような「罰」が実施されていくことになってしまうかも知れません。
最近の「罰」に対する世間の風潮が、
生徒のためを思い、本気で教えようとしている先生方の気力を削いでしまっているのではないか、少し心配になります。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
☆毎月第3日曜日午後3時~ 社会人文章講座好評実施中!(1回のみの参加もできます)
すっかり秋らしくなりましたが、まだ半袖を着ている春風館の望月です。
さて、前回に引き続き体罰に関するお話しです。
前回は、
「身体的な苦痛や負荷を与えられたとき、それを不当な暴力と感じるか、正当な指導と受け止めるかは内面的な話し」
であり、まあ早い話しが「その時による」ので、
これは体罰だからダメ、ここまではOK、という線引をするのは難しいということについて書きました。
今回は、そもそも「罰」というものは何なのか、教育の場でなぜ必要なのかということについて考えてみたいと思います。
我々は社会で生きる上で、定められたルール(法)に照らし合わせて、
何か悪いことをすれば罰を受けることになっています。
交通違反をすれば「罰金」をとられたり、
詐欺をして捕まれば刑務所に入れられたりするわけです。
会社等の組織内で、「こういう場合は賞与カット」というような罰則を設けている場合もあるでしょう。
本の返却をしなかったので一時的に図書館が利用できなくなる、といったペナルティも、
一種の罰と言えるかも知れません。
こういう「罰」が何のためにあるかと言うと、
残念ながらそういう「罰」を設けておかないとそういうことをやっちゃう人がいるからで、
「罰」を用意しておくことで、犯罪の発生を抑止することが期待されるからでしょう。
では教育の場での「罰」はどうでしょうか?
例えば、宿題をやってこなかった子がげんこつをもらう、
授業中おしゃべりしていた子が廊下に立たされる、
(今は両方NGです。)
期限内に課題を提出しなかったので量を増やされる、
(これはアリです)
こういった「罰」がいろいろあるのだと思います。
授業態度が悪いと内申点が下がる、というのも、とりようによってはある種の「罰」だと考えられるかも知れません。
やはり社会における法律による「罰」と同様に、
「罰」を用意することで、望ましくない行動を抑止するという目的があるように見えますが、
私は、教育の場での罰は、大人に対する罰とはちょっと質が違うものだと考えます。
もちろん抑止という意味合いもありますが、
それに偏重してしまったら、ただ単に「罰が嫌だからやらない」子が育ってしまうわけで、
「罰がなければやってもいい」「罰を受けても平気だったらやってもいい」という話しになってしまいます。
教育の場における「罰」は、もっと何かを「教える」ことが目的でなければなりません。
・自分のした行為が悪いことだと実感させ、分からせるために「罰」を与える。
・世の中にはルールがあり、守らなければならないということを分からせるために「罰」を与える。
・悪いことは悪い、違うことは違う、とはっきりした「けじめ」を教えるために「罰」を与える。
・自分が間違ったことをしてしまった場合、その責任をとることを教えるために「罰」を与える。
などなど。
社会に出た大人がお金を盗んだら犯罪で、捕まれば罰を受けます。
それは悪いと分かっていてやっているのですから、罰を受けるのです。(たまに分かっていない人もいるかも知れませんが)
しかし、成長過程にある子どもは、まだよく分かっていないことがたくさんあります。
教育の場で「罰」を与える場合は、社会のルールや常識、生きるために必要な心の持ち方といったものを教えて理解させることが目的であるはずです。
もっと言えば、罰を与える側は、自分が持っている人間としての正義や哲学といったものを伝える「気概」を有している必要があるのだと思います。
最近の教育現場では、
身体的苦痛を与えるのはNG、
暴言を吐くのはNG、
精神的苦痛を与えるのもNG、
という感じになってきているようですが、
何がNGなのかは
教育現場における「罰」というものの「目的」をふまえて論じるべきだと思います。
体罰に話しを戻せば、
前述したような目的に適うことが明確で、生徒のためになるのであれば、
殴るべきときは殴るべきだと私は考えます。
(ただし、実際には目的に適うかどうかはやってみないと分からず、逆効果になる危険性もあるので、
多くの場合教える側は内心の迷いや恐怖と戦いながら勇気をもって拳を振るうことになります。
でも、教える側というものは常にそういうものです)
悪いことをしようが怠けようが、先生は口ではいろいろ言ってもそれ以上は何もできない。
オレは何を言われても気にしないし、先生の言うことなんか聞かなくても平気だ、
と居直っている生徒もいるようです。
しかしそういう生徒は、誰かがいろんなリスクを背負ってでも、
自分を本気で殴ってくれるのを待ち望んでいるように見えることもあります。
繰り返しになりますが、教育の場での「罰」は子どものために、「教える」ために行われるものでなければなりません。
「こういう罰はNG、こういう罰はOK」
と表面的な規制を強めていくことで、
子どもにとって必要な「罰」が与えられず、
教育上はあまり意味がなく、逆効果になるような「罰」が実施されていくことになってしまうかも知れません。
最近の「罰」に対する世間の風潮が、
生徒のためを思い、本気で教えようとしている先生方の気力を削いでしまっているのではないか、少し心配になります。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
☆毎月第3日曜日午後3時~ 社会人文章講座好評実施中!(1回のみの参加もできます)
無料体験学習
お問合せ:054-201-9801
juku@shunpukan.net
随時受付中です
Posted by もちづき at 12:14│Comments(0)
│教育に関する話題
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |