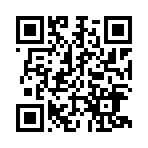無料体験学習
お問合せ:054-201-9801
juku@shunpukan.net
随時受付中です
2023年07月01日
学ぶ「意識」

こんにちは。今の中学生も「おーい!はに丸」を知っていたら、歴史の勉強で土偶とハニワを間違えることがないのになあ、と毎年考えてしまう春風館の望月です。
皆さん中間テストお疲れ様でした。中学生は今度は夏休み明けのテストに向けて長期戦の勉強をしていくことになります。特に受験生はこれから「いかに質の高い勉強をしていけるか」が重要となりますので、塾でも授業内で勉強の質を上げていくためのコツについていろいろとお伝えしていこうと思います。
テスト明けの授業でお話しした内容について、ここでも少しご紹介しておきます。
運動でも音楽でも学校の勉強でも、何かを学ぶ際にはまず「意識」が大切です。真剣に学ぼうとする意識を強く持つことができれば、勉強のやり方についても効果的な方法を自分から追求するようになるのでどんどん効率が上がり、上達が速くなります。逆に学ぼうとする意識が低い場合は、どんなに分かりやすく教えてもらっても、どんなに素晴らしい教材を使っても効果は上がりません。
意識を高める方法はいろいろありますが、中学生の皆さんには、「その場の空気や仲間の雰囲気を味方にする」やり方が一番やりやすく効果的だと思います。
例えば部活の練習で自分が上手くなりたいと思っているとき、他の部員たちの意識が高く、頑張ろう、上手くなろうと全員で真剣に取り組んでいる中で練習する場合と、他の部員の意識が低く、自分以外は上手くなろうとは思わずに適当にやっている中で練習する場合を考えてみて下さい。上達するのにどちらが有利か明らかです。
意識が高い雰囲気の中で、みんなで一緒に上達していくやり方は、ひとりだけで頑張るのに比べてずっと勢いがあります。部活でも勉強でも、体育祭の競技や合唱のようなものでもそうですが、みんなで頑張ろうという状態になっているときは、みんなが伸びていきます。
「家だとなかなかやらないけど塾だと勉強がはかどる」という人がよくいますが、それは塾には先生がいて叱られるからはかどるのではなくて、意識を高めやすい有利な空間で勉強できているからなのです。
学校でも教室の生徒全員が揃って意識を高め、教室内をよい空間にして毎回の授業を受けられるとよいのですが、個人差のある大人数の生徒が揃って、というのはなかなか難しい場合もあるようです。
その点春風館は小さな塾ですから、その日に集まっている少人数の皆さんがそれぞれ勉強しようという意識を持つことで、勉強のはかどる強固な空間を作ることができます。お互いのために、これからもみんなでより良い空間づくりを意識していきましょう。
塾生の皆さんには塾内で意識を高める具体的なコツについて詳しくお話ししたつもりです。
これからもいろんな情報をお伝えしていこうと思っていますので、特に受験生は入試に向けて早いうちからどんどん意識を高めていくようにして下さい。
小中学生の学習指導に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
http://shunpukan.net/index.html
社会人文章講座・「あきを先生を語る会」についてのお知らせは
https://www.facebook.com/shunpukanbunsho/
皆さん中間テストお疲れ様でした。中学生は今度は夏休み明けのテストに向けて長期戦の勉強をしていくことになります。特に受験生はこれから「いかに質の高い勉強をしていけるか」が重要となりますので、塾でも授業内で勉強の質を上げていくためのコツについていろいろとお伝えしていこうと思います。
テスト明けの授業でお話しした内容について、ここでも少しご紹介しておきます。
運動でも音楽でも学校の勉強でも、何かを学ぶ際にはまず「意識」が大切です。真剣に学ぼうとする意識を強く持つことができれば、勉強のやり方についても効果的な方法を自分から追求するようになるのでどんどん効率が上がり、上達が速くなります。逆に学ぼうとする意識が低い場合は、どんなに分かりやすく教えてもらっても、どんなに素晴らしい教材を使っても効果は上がりません。
意識を高める方法はいろいろありますが、中学生の皆さんには、「その場の空気や仲間の雰囲気を味方にする」やり方が一番やりやすく効果的だと思います。
例えば部活の練習で自分が上手くなりたいと思っているとき、他の部員たちの意識が高く、頑張ろう、上手くなろうと全員で真剣に取り組んでいる中で練習する場合と、他の部員の意識が低く、自分以外は上手くなろうとは思わずに適当にやっている中で練習する場合を考えてみて下さい。上達するのにどちらが有利か明らかです。
意識が高い雰囲気の中で、みんなで一緒に上達していくやり方は、ひとりだけで頑張るのに比べてずっと勢いがあります。部活でも勉強でも、体育祭の競技や合唱のようなものでもそうですが、みんなで頑張ろうという状態になっているときは、みんなが伸びていきます。
「家だとなかなかやらないけど塾だと勉強がはかどる」という人がよくいますが、それは塾には先生がいて叱られるからはかどるのではなくて、意識を高めやすい有利な空間で勉強できているからなのです。
学校でも教室の生徒全員が揃って意識を高め、教室内をよい空間にして毎回の授業を受けられるとよいのですが、個人差のある大人数の生徒が揃って、というのはなかなか難しい場合もあるようです。
その点春風館は小さな塾ですから、その日に集まっている少人数の皆さんがそれぞれ勉強しようという意識を持つことで、勉強のはかどる強固な空間を作ることができます。お互いのために、これからもみんなでより良い空間づくりを意識していきましょう。
塾生の皆さんには塾内で意識を高める具体的なコツについて詳しくお話ししたつもりです。
これからもいろんな情報をお伝えしていこうと思っていますので、特に受験生は入試に向けて早いうちからどんどん意識を高めていくようにして下さい。
小中学生の学習指導に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
http://shunpukan.net/index.html
社会人文章講座・「あきを先生を語る会」についてのお知らせは
https://www.facebook.com/shunpukanbunsho/
2023年05月31日
作文の課題

皆さんこんにちは。
6月に入ると今年ももう半分が終わってしまうのかとちょっぴり焦りを感じる春風館の望月です。
城内中はいよいよ明日から前期中間テスト本番です。これまで勉強してきたことをよく見直して、
当日実力を発揮できるように準備して挑んでもらえたらと思います。
末広中も15日の定期テストに向けての勉強が始まっていますが、
中3生は先週作文の課題が出され、本日が締め切りということでそれぞれ頑張って仕上げてくれていたようです。
春風館の授業内でもアドバイスなどの対応をさせてもらいましたが、
皆それぞれ自分の選んだテーマについて素直に語ることができていて、
なかなかよい作文が書けていたように感じました。
人の考えというものは思ったり考えたりしている段階ではまだ曖昧な状態にあり、
言語化、文章化することで整理されはっきりとしたものにできると言われています。
(国語教師あきを先生の受け売りですが…)
日本語を使いこなし、論理的に、読む人が分かるように文章を書けるということは、
勉強をする上で非常に大切な能力です。
忙しいテスト期間中に出された課題で苦労した人もいたようでしたが、
自分の考えに向き合って、それを言葉にする作業はとても大切な訓練になります。
各教科の勉強に時間を割かなければならず、なかなかじっくり作文の練習をする時間はとれませんが、
引き続き塾の授業や講習の中で、国語力を高める機会を確保していきたいと思います。
学校の授業や高校入試でもますます説明する力が求められるようになってきています。
普段から意識して国語の力を高めていきましょう!
小中学生の学習指導に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
http://shunpukan.net/index.html
社会人文章講座・「あきを先生を語る会」についてのお知らせは
https://www.facebook.com/shunpukanbunsho/
6月に入ると今年ももう半分が終わってしまうのかとちょっぴり焦りを感じる春風館の望月です。
城内中はいよいよ明日から前期中間テスト本番です。これまで勉強してきたことをよく見直して、
当日実力を発揮できるように準備して挑んでもらえたらと思います。
末広中も15日の定期テストに向けての勉強が始まっていますが、
中3生は先週作文の課題が出され、本日が締め切りということでそれぞれ頑張って仕上げてくれていたようです。
春風館の授業内でもアドバイスなどの対応をさせてもらいましたが、
皆それぞれ自分の選んだテーマについて素直に語ることができていて、
なかなかよい作文が書けていたように感じました。
人の考えというものは思ったり考えたりしている段階ではまだ曖昧な状態にあり、
言語化、文章化することで整理されはっきりとしたものにできると言われています。
(国語教師あきを先生の受け売りですが…)
日本語を使いこなし、論理的に、読む人が分かるように文章を書けるということは、
勉強をする上で非常に大切な能力です。
忙しいテスト期間中に出された課題で苦労した人もいたようでしたが、
自分の考えに向き合って、それを言葉にする作業はとても大切な訓練になります。
各教科の勉強に時間を割かなければならず、なかなかじっくり作文の練習をする時間はとれませんが、
引き続き塾の授業や講習の中で、国語力を高める機会を確保していきたいと思います。
学校の授業や高校入試でもますます説明する力が求められるようになってきています。
普段から意識して国語の力を高めていきましょう!
小中学生の学習指導に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
http://shunpukan.net/index.html
社会人文章講座・「あきを先生を語る会」についてのお知らせは
https://www.facebook.com/shunpukanbunsho/
2014年02月04日
成果が出たのは

こんにちは。意外にパソコン作業が多いので、最近「ブルーライトをカットするめがね」を試してみている春風館の望月です。
さて、点数や成績が上がった等、何か結果が出た際に、ご家庭から塾に対してお礼を言って下さることがあります。
喜んでいただいてお礼を言っていただけるのはもちろん嬉しいことではあるのですが、
では、実際のところ、学力が上がったり、点数などのかたちで目に見える成果が出た理由はどこにあるのでしょうか?
それはもう、当たり前のことですが「本人が努力して勉強したから」です。
塾講師など無力なもので、どんなに息巻いて授業をやろうが、教材を研究して創意工夫しようが、
本人ががんばらない限り何の成果も出ません。
逆に本人さえその気になってがんばりさえすれば、よほどめちゃくちゃな教え方をしない限りどんどん学力は上がっていきます。
そんなわけで、こちらの仕事というのはもっぱら「どうにかして本人にがんばってもらうようにがんばる」ということになるのですが、
たかが1人の人間が、他の人間が努力をするように仕向けるなどそもそも思い上がった行為であり、
ほんとにもう、いろんなことを考えていろいろやってみても、こちらができることというのは本当に微々たるものであるように感じます。
「オレが勉強することで生徒の学力が上がるならこんなにカンタンなことはないのに・・・」と思ったことがある塾講師は、私以外にもたくさんいるのではないでしょうか?
それでも、とにかくがんばって情熱を傾けるしかないのですけれども。
ちょっととりとめのない話しになってしまいましたが、つまり何が言いたいかと申しますと、
結果が出たのは本人ががんばったからであり、
その「がんばれた自分」をご本人にもご家庭にもしっかり認めてもらって、今後の活力にしていって欲しいなあと、
そういうことでございます。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
☆毎月第3日曜日午後3時~ 社会人文章講座好評実施中!(1回のみの参加もできます)
さて、点数や成績が上がった等、何か結果が出た際に、ご家庭から塾に対してお礼を言って下さることがあります。
喜んでいただいてお礼を言っていただけるのはもちろん嬉しいことではあるのですが、
では、実際のところ、学力が上がったり、点数などのかたちで目に見える成果が出た理由はどこにあるのでしょうか?
それはもう、当たり前のことですが「本人が努力して勉強したから」です。
塾講師など無力なもので、どんなに息巻いて授業をやろうが、教材を研究して創意工夫しようが、
本人ががんばらない限り何の成果も出ません。
逆に本人さえその気になってがんばりさえすれば、よほどめちゃくちゃな教え方をしない限りどんどん学力は上がっていきます。
そんなわけで、こちらの仕事というのはもっぱら「どうにかして本人にがんばってもらうようにがんばる」ということになるのですが、
たかが1人の人間が、他の人間が努力をするように仕向けるなどそもそも思い上がった行為であり、
ほんとにもう、いろんなことを考えていろいろやってみても、こちらができることというのは本当に微々たるものであるように感じます。
「オレが勉強することで生徒の学力が上がるならこんなにカンタンなことはないのに・・・」と思ったことがある塾講師は、私以外にもたくさんいるのではないでしょうか?
それでも、とにかくがんばって情熱を傾けるしかないのですけれども。
ちょっととりとめのない話しになってしまいましたが、つまり何が言いたいかと申しますと、
結果が出たのは本人ががんばったからであり、
その「がんばれた自分」をご本人にもご家庭にもしっかり認めてもらって、今後の活力にしていって欲しいなあと、
そういうことでございます。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
☆毎月第3日曜日午後3時~ 社会人文章講座好評実施中!(1回のみの参加もできます)
2013年10月10日
先生の思い出①

こんにちは。
最近、外気に比べて教室内が暑くなるのだけれど、
風邪気味の子が心配なのでエアコンや扇風機を使うのを迷ってしまう春風館の望月です。
たまたまかも知れませんが、
最近、ネットなどで学校の先生の指導力不足を批判する記述を目にすることが増えた気がします。
(小学生の全国学力調査で、静岡の国語の結果が最下位だったことも一因かも知れません)
「昔はいい先生がいっぱいいたのに」なんて声も聞きますし、
「昔からひどい先生はいっぱいいたよ」なんて声も聞きますが、
全体的な話しとして、学校の先生の質は以前に比べて下がってきてしまっているのでしょうか?
「先生の質」というものを論じ始めると、またいろいろと長いお話しになってしまいますが・・・
個人的には、個々の先生の質はともかく、
「先生を取り巻く環境」が、数十年前に比べて大きく変化し、先生が指導をしにくくなっていることは確かなんじゃないかなあ、と
そういうことは感じています。
もしそういう中で、子どもたちが「尊敬できる先生」に出会う機会が減ってしまっているとしたら残念なことです。
さて、前置きが長くなりましたが、これからときどき、
私自身の「先生の思い出」を書いていきたいと思います。
私も先生に対してよい思い出もあれば悪い思い出もありますが、
尊敬できる先生に出会い、敬意を持った経験が確かにあります。
そういう経験をご紹介することが、今の時代に少し意味があるような気がするので、
これからそういった思い出を不定期に書き綴ってみたいと思います。
<先生の思い出① 厳しいと怖がられていた女の先生>
中学生のとき、厳しいと評判の(?)女性の先生に教わったことがありました。
学生服の違反を見つけたときなどは襟をつかんで
「やるじゃないか! あたいのクラスで!」などと大声で怒鳴りつけ、
男子生徒を涙目にさせて震え上がらせるような先生でした。
叱った場合もそれを引きずることはせず、普段はにこやかで優しい。
誰がやっても悪いことは悪い。
言うことが一貫していて、はっきりと「ケジメ」をつける先生でした。
言うことが一貫していて、ケジメをつけられるというのは指導者として非常に大切なことだと思います。
この先生の担当するクラスは、毎年合唱コンクールなどのイベントに強く、
そういうふうにクラスを持っていくことできる力があったのだろうなあ、と感じさせられます。
さて、あるときその先生が「怒った」ことがありました。
ある男子生徒が、体型の太った女子生徒のことを茶化すようなことを言ったからです。
まあ、中学生がそういう悪口を言うのは日常茶飯事ですし、そんなに珍しいことではないようにも感じたのですが、
このとき先生はその生徒を皆の前で「大々的に」怒りました。
「私は普段、叱ることはあっても怒らない。怒るのは、体の特徴など、本人の努力等とは関係ないことをけなしたときと、
自分の体を粗末に扱ったときだ」
先生はみんなに、そのような説明をしました。
私は常々、この先生は大声で怒鳴りつけたりはするけれど、内心は別に怒っていなくて、
びびらせるためにわざとやっているんだろうなあ、と感じていました。
この説明を聞いて、先生が「叱る」と「怒る」を区別していたので、
そうか、やはりなあと納得したのを覚えています。
そのときの機嫌によって態度が変わったり、
感情的になって関係ない人まで怒鳴りつけたりする人もいるわけですが、
この先生は「大人」なのだなあ、と思いました。
そして、そんな「大人」でも、感情をぶつけ、自分の生理的な反応をはっきりと見せるときがある。
演技として叱りつけるのではなく、心から怒るときがある。
だとしたら、先生が怒ること(人の身体的特徴をけなすこと、自分の体を粗末にすること)は、
よほど悪いことなのだなあ、気をつけなければなあ、と学習しました。
今思えば、このときでさえも、先生は非常に理性的に全体への指導意義を考えて、
場を演出していたのでしょう。
しかし、その現場を見た先生が反射的に状況をキャッチし、反応できたのは、
「腹が立った」という自分の感覚があったからだと思います。
私は
「指導する側は叱ることはあってもまず怒ってはならない。
しかし、自分の信念や哲学に基づいて、本気で怒って感情を見せるべきときもある。」
という考えでいますが・・・
こういう先生に教わった経験が、自分の指導方針に大きな影響を与えているのは間違いないことだと思います。
先生というのは非常に難しい仕事です。
その難しい仕事に立ち向かい、戦う人がいます。
学校に限らず、塾や道場や習い事の教室などなど、いろんなところでがんばっている先生がいます。
これからも不定期に、今回のような「先生の思い出」をご紹介していきたいと思います。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
☆毎月第3日曜日午後3時~ 社会人文章講座好評実施中!(1回のみの参加もできます)
最近、外気に比べて教室内が暑くなるのだけれど、
風邪気味の子が心配なのでエアコンや扇風機を使うのを迷ってしまう春風館の望月です。
たまたまかも知れませんが、
最近、ネットなどで学校の先生の指導力不足を批判する記述を目にすることが増えた気がします。
(小学生の全国学力調査で、静岡の国語の結果が最下位だったことも一因かも知れません)
「昔はいい先生がいっぱいいたのに」なんて声も聞きますし、
「昔からひどい先生はいっぱいいたよ」なんて声も聞きますが、
全体的な話しとして、学校の先生の質は以前に比べて下がってきてしまっているのでしょうか?
「先生の質」というものを論じ始めると、またいろいろと長いお話しになってしまいますが・・・
個人的には、個々の先生の質はともかく、
「先生を取り巻く環境」が、数十年前に比べて大きく変化し、先生が指導をしにくくなっていることは確かなんじゃないかなあ、と
そういうことは感じています。
もしそういう中で、子どもたちが「尊敬できる先生」に出会う機会が減ってしまっているとしたら残念なことです。
さて、前置きが長くなりましたが、これからときどき、
私自身の「先生の思い出」を書いていきたいと思います。
私も先生に対してよい思い出もあれば悪い思い出もありますが、
尊敬できる先生に出会い、敬意を持った経験が確かにあります。
そういう経験をご紹介することが、今の時代に少し意味があるような気がするので、
これからそういった思い出を不定期に書き綴ってみたいと思います。
<先生の思い出① 厳しいと怖がられていた女の先生>
中学生のとき、厳しいと評判の(?)女性の先生に教わったことがありました。
学生服の違反を見つけたときなどは襟をつかんで
「やるじゃないか! あたいのクラスで!」などと大声で怒鳴りつけ、
男子生徒を涙目にさせて震え上がらせるような先生でした。
叱った場合もそれを引きずることはせず、普段はにこやかで優しい。
誰がやっても悪いことは悪い。
言うことが一貫していて、はっきりと「ケジメ」をつける先生でした。
言うことが一貫していて、ケジメをつけられるというのは指導者として非常に大切なことだと思います。
この先生の担当するクラスは、毎年合唱コンクールなどのイベントに強く、
そういうふうにクラスを持っていくことできる力があったのだろうなあ、と感じさせられます。
さて、あるときその先生が「怒った」ことがありました。
ある男子生徒が、体型の太った女子生徒のことを茶化すようなことを言ったからです。
まあ、中学生がそういう悪口を言うのは日常茶飯事ですし、そんなに珍しいことではないようにも感じたのですが、
このとき先生はその生徒を皆の前で「大々的に」怒りました。
「私は普段、叱ることはあっても怒らない。怒るのは、体の特徴など、本人の努力等とは関係ないことをけなしたときと、
自分の体を粗末に扱ったときだ」
先生はみんなに、そのような説明をしました。
私は常々、この先生は大声で怒鳴りつけたりはするけれど、内心は別に怒っていなくて、
びびらせるためにわざとやっているんだろうなあ、と感じていました。
この説明を聞いて、先生が「叱る」と「怒る」を区別していたので、
そうか、やはりなあと納得したのを覚えています。
そのときの機嫌によって態度が変わったり、
感情的になって関係ない人まで怒鳴りつけたりする人もいるわけですが、
この先生は「大人」なのだなあ、と思いました。
そして、そんな「大人」でも、感情をぶつけ、自分の生理的な反応をはっきりと見せるときがある。
演技として叱りつけるのではなく、心から怒るときがある。
だとしたら、先生が怒ること(人の身体的特徴をけなすこと、自分の体を粗末にすること)は、
よほど悪いことなのだなあ、気をつけなければなあ、と学習しました。
今思えば、このときでさえも、先生は非常に理性的に全体への指導意義を考えて、
場を演出していたのでしょう。
しかし、その現場を見た先生が反射的に状況をキャッチし、反応できたのは、
「腹が立った」という自分の感覚があったからだと思います。
私は
「指導する側は叱ることはあってもまず怒ってはならない。
しかし、自分の信念や哲学に基づいて、本気で怒って感情を見せるべきときもある。」
という考えでいますが・・・
こういう先生に教わった経験が、自分の指導方針に大きな影響を与えているのは間違いないことだと思います。
先生というのは非常に難しい仕事です。
その難しい仕事に立ち向かい、戦う人がいます。
学校に限らず、塾や道場や習い事の教室などなど、いろんなところでがんばっている先生がいます。
これからも不定期に、今回のような「先生の思い出」をご紹介していきたいと思います。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
☆毎月第3日曜日午後3時~ 社会人文章講座好評実施中!(1回のみの参加もできます)
2013年10月03日
負荷をかけること(体罰について③)

こんにちは。ここ数日、暑くてびっくりな春風館の望月です。
前回、前々回と体罰について書かせていただきましたが、
今日もそれと少し関連するお話しとして、
教育の場で「負荷をかけること」について述べてみたいと思います。
体罰を禁止しようという場合、
一般論としては、「体罰による身体的苦痛を与えなくても指導ができるはずだ」
という考えが前提にあるのだと思います。
では体罰を抜きにどのように指導するかというお話しになりますが、ここで
「身体的苦痛を与えなくても口で言えばよい」となると、
その前提として
「身体的苦痛を与えなくても精神的苦痛を与えればよい」
という考え方があるように聞こえてしまいます。
となると、今度は「体罰にならないからと言って言葉の暴力をふるうのはひどいじゃないか」
というお話しになり、
「苦痛を与えなくても指導はできるはずだ」というお話しになってきます。
※私個人は前回述べた通り、
本人に何かを教えるために、その本人のためになるのであれば、
身体的苦痛を与えることも精神的苦痛を与えることも時には必要だと考えていますし、
そういうきちんとした目的がないのであれば、体罰であるないに関わらず、苦痛は与えるべきではないと考えています。
でも、ちょっと待って下さい。
「苦痛を与えることなしに、教育をすること」はできるのでしょうか?
何度も言う通り、本人のためにならないような(なるかどうか考えてもいないような)苦痛を与えることには反対です。
しかし、成長するためには何らかの「負荷」が必要で、
負荷がかかればストレスも感じ、苦痛も味わうものです。
負荷のない運動では身体は鍛えられません。
勉強だって「めんどくさい、嫌だ、考えるのが辛い」と感じることに向きあうから脳が成長していくのです。
負荷に耐えるから心も鍛えられていくのです。
苦痛を与えることが何でも悪なら、
「本人が嫌がるのに難しい問題に取り組ませた」
「本人が辛いと言っているのにたくさん漢字を書かせた」
「本人が今テレビを見たいと言っているのに見させてあげなかった」
といったことも「ひどい」「体罰だ」というお話しになってしまいます。
なるべく負荷をかけない環境をつくり、
がんばらせず、がまんもさせずに子どもを育てていけば、
頭も身体も心も弱いまま大きくなっていきます。
そういう子たちが弱いまま、近い将来、厳しく不条理にあふれた負荷だらけの社会に放り出される。
そんな恐ろしいことがあってよいはずがありません。
もちろん、本人が耐え切れないほどの負荷をかけて潰してしまうのでは困りますし、
状況によって(例えば、虐待を受けて心に深い傷を負っている場合など)は、
なるべく負荷をかけず、すべてを許し、まずは本当に安心してもらう状態をつくることが必要な場合もあります。
しかし、間違った負荷のかけ方で起きてしまった不幸な事件ばかりを騒ぎたて、
なんでもかんでも罰はダメ、負荷はダメとしてしまうのでは、よい教育の環境をつくっていくのは難しいのではないでしょうか。
教育の場で罰を与えることや苦痛を与えることについて是非を問う場合、
現場をよく知った上で、よくよく考えて論じる必要があるように感じます。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
☆毎月第3日曜日午後3時~ 社会人文章講座好評実施中!(1回のみの参加もできます)
今回の記事は続きがあります。
余談となりますが、お時間のある方はクリックしてご覧下さい。
続きを読む
前回、前々回と体罰について書かせていただきましたが、
今日もそれと少し関連するお話しとして、
教育の場で「負荷をかけること」について述べてみたいと思います。
体罰を禁止しようという場合、
一般論としては、「体罰による身体的苦痛を与えなくても指導ができるはずだ」
という考えが前提にあるのだと思います。
では体罰を抜きにどのように指導するかというお話しになりますが、ここで
「身体的苦痛を与えなくても口で言えばよい」となると、
その前提として
「身体的苦痛を与えなくても精神的苦痛を与えればよい」
という考え方があるように聞こえてしまいます。
となると、今度は「体罰にならないからと言って言葉の暴力をふるうのはひどいじゃないか」
というお話しになり、
「苦痛を与えなくても指導はできるはずだ」というお話しになってきます。
※私個人は前回述べた通り、
本人に何かを教えるために、その本人のためになるのであれば、
身体的苦痛を与えることも精神的苦痛を与えることも時には必要だと考えていますし、
そういうきちんとした目的がないのであれば、体罰であるないに関わらず、苦痛は与えるべきではないと考えています。
でも、ちょっと待って下さい。
「苦痛を与えることなしに、教育をすること」はできるのでしょうか?
何度も言う通り、本人のためにならないような(なるかどうか考えてもいないような)苦痛を与えることには反対です。
しかし、成長するためには何らかの「負荷」が必要で、
負荷がかかればストレスも感じ、苦痛も味わうものです。
負荷のない運動では身体は鍛えられません。
勉強だって「めんどくさい、嫌だ、考えるのが辛い」と感じることに向きあうから脳が成長していくのです。
負荷に耐えるから心も鍛えられていくのです。
苦痛を与えることが何でも悪なら、
「本人が嫌がるのに難しい問題に取り組ませた」
「本人が辛いと言っているのにたくさん漢字を書かせた」
「本人が今テレビを見たいと言っているのに見させてあげなかった」
といったことも「ひどい」「体罰だ」というお話しになってしまいます。
なるべく負荷をかけない環境をつくり、
がんばらせず、がまんもさせずに子どもを育てていけば、
頭も身体も心も弱いまま大きくなっていきます。
そういう子たちが弱いまま、近い将来、厳しく不条理にあふれた負荷だらけの社会に放り出される。
そんな恐ろしいことがあってよいはずがありません。
もちろん、本人が耐え切れないほどの負荷をかけて潰してしまうのでは困りますし、
状況によって(例えば、虐待を受けて心に深い傷を負っている場合など)は、
なるべく負荷をかけず、すべてを許し、まずは本当に安心してもらう状態をつくることが必要な場合もあります。
しかし、間違った負荷のかけ方で起きてしまった不幸な事件ばかりを騒ぎたて、
なんでもかんでも罰はダメ、負荷はダメとしてしまうのでは、よい教育の環境をつくっていくのは難しいのではないでしょうか。
教育の場で罰を与えることや苦痛を与えることについて是非を問う場合、
現場をよく知った上で、よくよく考えて論じる必要があるように感じます。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
☆毎月第3日曜日午後3時~ 社会人文章講座好評実施中!(1回のみの参加もできます)
今回の記事は続きがあります。
余談となりますが、お時間のある方はクリックしてご覧下さい。
続きを読む
2013年10月01日
教育の場での罰(体罰について②)

こんにちは。
すっかり秋らしくなりましたが、まだ半袖を着ている春風館の望月です。
さて、前回に引き続き体罰に関するお話しです。
前回は、
「身体的な苦痛や負荷を与えられたとき、それを不当な暴力と感じるか、正当な指導と受け止めるかは内面的な話し」
であり、まあ早い話しが「その時による」ので、
これは体罰だからダメ、ここまではOK、という線引をするのは難しいということについて書きました。
今回は、そもそも「罰」というものは何なのか、教育の場でなぜ必要なのかということについて考えてみたいと思います。
我々は社会で生きる上で、定められたルール(法)に照らし合わせて、
何か悪いことをすれば罰を受けることになっています。
交通違反をすれば「罰金」をとられたり、
詐欺をして捕まれば刑務所に入れられたりするわけです。
会社等の組織内で、「こういう場合は賞与カット」というような罰則を設けている場合もあるでしょう。
本の返却をしなかったので一時的に図書館が利用できなくなる、といったペナルティも、
一種の罰と言えるかも知れません。
こういう「罰」が何のためにあるかと言うと、
残念ながらそういう「罰」を設けておかないとそういうことをやっちゃう人がいるからで、
「罰」を用意しておくことで、犯罪の発生を抑止することが期待されるからでしょう。
では教育の場での「罰」はどうでしょうか?
例えば、宿題をやってこなかった子がげんこつをもらう、
授業中おしゃべりしていた子が廊下に立たされる、
(今は両方NGです。)
期限内に課題を提出しなかったので量を増やされる、
(これはアリです)
こういった「罰」がいろいろあるのだと思います。
授業態度が悪いと内申点が下がる、というのも、とりようによってはある種の「罰」だと考えられるかも知れません。
やはり社会における法律による「罰」と同様に、
「罰」を用意することで、望ましくない行動を抑止するという目的があるように見えますが、
私は、教育の場での罰は、大人に対する罰とはちょっと質が違うものだと考えます。
もちろん抑止という意味合いもありますが、
それに偏重してしまったら、ただ単に「罰が嫌だからやらない」子が育ってしまうわけで、
「罰がなければやってもいい」「罰を受けても平気だったらやってもいい」という話しになってしまいます。
教育の場における「罰」は、もっと何かを「教える」ことが目的でなければなりません。
・自分のした行為が悪いことだと実感させ、分からせるために「罰」を与える。
・世の中にはルールがあり、守らなければならないということを分からせるために「罰」を与える。
・悪いことは悪い、違うことは違う、とはっきりした「けじめ」を教えるために「罰」を与える。
・自分が間違ったことをしてしまった場合、その責任をとることを教えるために「罰」を与える。
などなど。
社会に出た大人がお金を盗んだら犯罪で、捕まれば罰を受けます。
それは悪いと分かっていてやっているのですから、罰を受けるのです。(たまに分かっていない人もいるかも知れませんが)
しかし、成長過程にある子どもは、まだよく分かっていないことがたくさんあります。
教育の場で「罰」を与える場合は、社会のルールや常識、生きるために必要な心の持ち方といったものを教えて理解させることが目的であるはずです。
もっと言えば、罰を与える側は、自分が持っている人間としての正義や哲学といったものを伝える「気概」を有している必要があるのだと思います。
最近の教育現場では、
身体的苦痛を与えるのはNG、
暴言を吐くのはNG、
精神的苦痛を与えるのもNG、
という感じになってきているようですが、
何がNGなのかは
教育現場における「罰」というものの「目的」をふまえて論じるべきだと思います。
体罰に話しを戻せば、
前述したような目的に適うことが明確で、生徒のためになるのであれば、
殴るべきときは殴るべきだと私は考えます。
(ただし、実際には目的に適うかどうかはやってみないと分からず、逆効果になる危険性もあるので、
多くの場合教える側は内心の迷いや恐怖と戦いながら勇気をもって拳を振るうことになります。
でも、教える側というものは常にそういうものです)
悪いことをしようが怠けようが、先生は口ではいろいろ言ってもそれ以上は何もできない。
オレは何を言われても気にしないし、先生の言うことなんか聞かなくても平気だ、
と居直っている生徒もいるようです。
しかしそういう生徒は、誰かがいろんなリスクを背負ってでも、
自分を本気で殴ってくれるのを待ち望んでいるように見えることもあります。
繰り返しになりますが、教育の場での「罰」は子どものために、「教える」ために行われるものでなければなりません。
「こういう罰はNG、こういう罰はOK」
と表面的な規制を強めていくことで、
子どもにとって必要な「罰」が与えられず、
教育上はあまり意味がなく、逆効果になるような「罰」が実施されていくことになってしまうかも知れません。
最近の「罰」に対する世間の風潮が、
生徒のためを思い、本気で教えようとしている先生方の気力を削いでしまっているのではないか、少し心配になります。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
☆毎月第3日曜日午後3時~ 社会人文章講座好評実施中!(1回のみの参加もできます)
すっかり秋らしくなりましたが、まだ半袖を着ている春風館の望月です。
さて、前回に引き続き体罰に関するお話しです。
前回は、
「身体的な苦痛や負荷を与えられたとき、それを不当な暴力と感じるか、正当な指導と受け止めるかは内面的な話し」
であり、まあ早い話しが「その時による」ので、
これは体罰だからダメ、ここまではOK、という線引をするのは難しいということについて書きました。
今回は、そもそも「罰」というものは何なのか、教育の場でなぜ必要なのかということについて考えてみたいと思います。
我々は社会で生きる上で、定められたルール(法)に照らし合わせて、
何か悪いことをすれば罰を受けることになっています。
交通違反をすれば「罰金」をとられたり、
詐欺をして捕まれば刑務所に入れられたりするわけです。
会社等の組織内で、「こういう場合は賞与カット」というような罰則を設けている場合もあるでしょう。
本の返却をしなかったので一時的に図書館が利用できなくなる、といったペナルティも、
一種の罰と言えるかも知れません。
こういう「罰」が何のためにあるかと言うと、
残念ながらそういう「罰」を設けておかないとそういうことをやっちゃう人がいるからで、
「罰」を用意しておくことで、犯罪の発生を抑止することが期待されるからでしょう。
では教育の場での「罰」はどうでしょうか?
例えば、宿題をやってこなかった子がげんこつをもらう、
授業中おしゃべりしていた子が廊下に立たされる、
(今は両方NGです。)
期限内に課題を提出しなかったので量を増やされる、
(これはアリです)
こういった「罰」がいろいろあるのだと思います。
授業態度が悪いと内申点が下がる、というのも、とりようによってはある種の「罰」だと考えられるかも知れません。
やはり社会における法律による「罰」と同様に、
「罰」を用意することで、望ましくない行動を抑止するという目的があるように見えますが、
私は、教育の場での罰は、大人に対する罰とはちょっと質が違うものだと考えます。
もちろん抑止という意味合いもありますが、
それに偏重してしまったら、ただ単に「罰が嫌だからやらない」子が育ってしまうわけで、
「罰がなければやってもいい」「罰を受けても平気だったらやってもいい」という話しになってしまいます。
教育の場における「罰」は、もっと何かを「教える」ことが目的でなければなりません。
・自分のした行為が悪いことだと実感させ、分からせるために「罰」を与える。
・世の中にはルールがあり、守らなければならないということを分からせるために「罰」を与える。
・悪いことは悪い、違うことは違う、とはっきりした「けじめ」を教えるために「罰」を与える。
・自分が間違ったことをしてしまった場合、その責任をとることを教えるために「罰」を与える。
などなど。
社会に出た大人がお金を盗んだら犯罪で、捕まれば罰を受けます。
それは悪いと分かっていてやっているのですから、罰を受けるのです。(たまに分かっていない人もいるかも知れませんが)
しかし、成長過程にある子どもは、まだよく分かっていないことがたくさんあります。
教育の場で「罰」を与える場合は、社会のルールや常識、生きるために必要な心の持ち方といったものを教えて理解させることが目的であるはずです。
もっと言えば、罰を与える側は、自分が持っている人間としての正義や哲学といったものを伝える「気概」を有している必要があるのだと思います。
最近の教育現場では、
身体的苦痛を与えるのはNG、
暴言を吐くのはNG、
精神的苦痛を与えるのもNG、
という感じになってきているようですが、
何がNGなのかは
教育現場における「罰」というものの「目的」をふまえて論じるべきだと思います。
体罰に話しを戻せば、
前述したような目的に適うことが明確で、生徒のためになるのであれば、
殴るべきときは殴るべきだと私は考えます。
(ただし、実際には目的に適うかどうかはやってみないと分からず、逆効果になる危険性もあるので、
多くの場合教える側は内心の迷いや恐怖と戦いながら勇気をもって拳を振るうことになります。
でも、教える側というものは常にそういうものです)
悪いことをしようが怠けようが、先生は口ではいろいろ言ってもそれ以上は何もできない。
オレは何を言われても気にしないし、先生の言うことなんか聞かなくても平気だ、
と居直っている生徒もいるようです。
しかしそういう生徒は、誰かがいろんなリスクを背負ってでも、
自分を本気で殴ってくれるのを待ち望んでいるように見えることもあります。
繰り返しになりますが、教育の場での「罰」は子どものために、「教える」ために行われるものでなければなりません。
「こういう罰はNG、こういう罰はOK」
と表面的な規制を強めていくことで、
子どもにとって必要な「罰」が与えられず、
教育上はあまり意味がなく、逆効果になるような「罰」が実施されていくことになってしまうかも知れません。
最近の「罰」に対する世間の風潮が、
生徒のためを思い、本気で教えようとしている先生方の気力を削いでしまっているのではないか、少し心配になります。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
☆毎月第3日曜日午後3時~ 社会人文章講座好評実施中!(1回のみの参加もできます)
2013年09月27日
体罰について

こんにちは。
最近、塾生のことで残念な気持ちになった日は辛くてお酒を飲み、
塾生ががんばってくれた日は嬉しくてやっぱりお酒を飲んでしまう春風館の望月です。
いろいろと体罰が問題になっています。
これについて語り始めると長くなってしまうのですが、話題がつきないので、
一度このブログでも触れておきたいと思います。
学校や塾といった教育の場で、例えば生徒をひっぱたく。
必要性があって叩くという行為は、果たしてアリかナシか。
(現在、教育現場では必要性の有無に関わらず叩くのはNGです)
私は、叩くという行為が必要な場合もあると思っているので、アリかナシかと言われれば「アリ」だと考えています。
まず前提として、
・指導する側がストレスやフラストレーションなどで精神的な疾患を抱えていて、そのために暴力をふるう。
・傷跡や後遺症が残ったり、回復するのに時間がかかるようなケガを負わせる。
こんなことは指導者の行為として論外ですので、はずして考えます。
また、殺し合いの現場にさらされる兵士の訓練などは特殊なお話しなので、別のお話しとして分けて考えます。
さらに、スポーツなどの競技の世界で、結果を求めるために体罰(暴力に限らず、苦痛を与えるような訓練を含む)を行うことについても、
今語りたい学校や塾での「体罰」とは別の話しとして分けて考えたいと思います。
さて、以上を前提として、学校や塾での体罰について述べてみたいと思います。
数十年前は忘れ物をすると先生に叩かれたり、態度が悪ければ正座をさせられたりということは珍しくない光景でした。
それが今は、「教育の場で暴力を使ったり、身体に負担をかけさせたりすることは前時代的な野蛮な行為で、禁止するべきだ」
というお話しになっているようです。
ここで問題になってきたのが、「どこまでが体罰か」という点です。
蹴ったり叩いたりといった暴力はもちろん体罰。さらに、正座をさせる、廊下に立たせる、ペナルティとして走らせたりするのも体罰。
文科省が出している「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」を見てみましょう。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331908.htm
立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず、席につかないため、頬をつねって席につかせる →体罰
宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた。 →体罰
学習課題や清掃活動を課す。→OK
殴りかかろうとする生徒を、押さえつけて制止させる。→OK
などなど。
個人的には、こういう具体的な基準を設けることはナンセンスじゃないかなあ、と感じます。
身体的な苦痛や負荷を与えられたとき、
それを不当な暴力と感じるか、正当な指導と受け止めるかは内面的な話しです。
例えばある生徒が大事な試合の日に寝坊して、遅刻して会場にやってきたとき、
仲間に対して申し訳なくて恥ずかしくて、どうしたらいいか分からず先生のところに行くと、
先生が「馬鹿野郎!」と一喝して大きなビンタをはる。
張り倒された生徒に先生は「早く着替えろ!」と怒鳴りつけ、後はもう遅刻のことには触れず、試合に突入していく。
それを見た仲間は、誰もその生徒を責めようとは考えません。
生徒は遅刻した分精一杯がんばろうと、大急ぎで着替え、仲間のもとに走っていきます。
このとき、生徒は先生のビンタによって救われているかも知れません。
もし私がその生徒なら、先生に感謝したと思います。
ビンタ一発によって、その数秒の行為で仲間や先生から「許し」を得て、気持ちを切り替えて試合に臨めたのです。
このとき、先生が体罰を用いず、
「今日は大事な試合なのに、お前は遅刻をして、みんなに迷惑をかけて、ウォーミングアップもできず・・・」
などなど口頭で説教をしたとしたらどうでしょう。
もし私がその生徒なら、意気消沈して試合どころではなくなる気がします。
逆に、先生が自分に対して愛情がなく、悪意を持っていると感じるなら、
それが軽く頭をはたく程度の行為でも、たたくフリだけでも、生徒は傷つき、精神的に大きな苦痛を感じるはずです。
叩くから悪い、口頭で注意しているからよい、というものではない気がします。
それを、外から見て「ここからここまでは暴力、ここまではOK」と線引きしようとするのは本質を見失っているやり方のような気がします。
(訴訟が起きた際に、円滑に裁判を進めるのには役立つかも知れませんが)
こういう基準を念頭に置きながら、慎重に指導にあたる現場の先生方は本当に大変だと思います。
指導するときはそのときそのときが勝負ですから、
「あれ、これ体罰になるんじゃね?」
「こういう言い方したら、後で問題になるんじゃね?」
なんていちいち考えている間に、もう動くべきタイミングは逸してしまいます。
教室でナイフを振り回した生徒を、後で殴った校長先生が辞めたそうですが、
私だったら教室でナイフを出した生徒を見た瞬間に殴り倒し、
とりあげたナイフで自分の手を切って
「お前はこうやって人を殺そうとしたんだ」
と血を見せるぐらいのことはすると思います。
問答無用で悪いことは悪いのです。
どんな事情があったとしてもそれはいけないことだ、ということを分からせるためには、
その瞬間に反射的なスピードでそれを知らせる必要があります。
そうでなければ「問答無用」ではなくなります。
教室で刃物を振り回す行為がいけないことだというのは、
とくとくと説明して分からせるようなことではないのです。
予想通りかなり長文になってまいりました。
この話題についてはまた日を改めて、引き続き述べてみたいと思います。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
☆毎月第3日曜日午後3時~ 社会人文章講座好評実施中!(1回のみの参加もできます)
最近、塾生のことで残念な気持ちになった日は辛くてお酒を飲み、
塾生ががんばってくれた日は嬉しくてやっぱりお酒を飲んでしまう春風館の望月です。
いろいろと体罰が問題になっています。
これについて語り始めると長くなってしまうのですが、話題がつきないので、
一度このブログでも触れておきたいと思います。
学校や塾といった教育の場で、例えば生徒をひっぱたく。
必要性があって叩くという行為は、果たしてアリかナシか。
(現在、教育現場では必要性の有無に関わらず叩くのはNGです)
私は、叩くという行為が必要な場合もあると思っているので、アリかナシかと言われれば「アリ」だと考えています。
まず前提として、
・指導する側がストレスやフラストレーションなどで精神的な疾患を抱えていて、そのために暴力をふるう。
・傷跡や後遺症が残ったり、回復するのに時間がかかるようなケガを負わせる。
こんなことは指導者の行為として論外ですので、はずして考えます。
また、殺し合いの現場にさらされる兵士の訓練などは特殊なお話しなので、別のお話しとして分けて考えます。
さらに、スポーツなどの競技の世界で、結果を求めるために体罰(暴力に限らず、苦痛を与えるような訓練を含む)を行うことについても、
今語りたい学校や塾での「体罰」とは別の話しとして分けて考えたいと思います。
さて、以上を前提として、学校や塾での体罰について述べてみたいと思います。
数十年前は忘れ物をすると先生に叩かれたり、態度が悪ければ正座をさせられたりということは珍しくない光景でした。
それが今は、「教育の場で暴力を使ったり、身体に負担をかけさせたりすることは前時代的な野蛮な行為で、禁止するべきだ」
というお話しになっているようです。
ここで問題になってきたのが、「どこまでが体罰か」という点です。
蹴ったり叩いたりといった暴力はもちろん体罰。さらに、正座をさせる、廊下に立たせる、ペナルティとして走らせたりするのも体罰。
文科省が出している「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」を見てみましょう。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331908.htm
立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず、席につかないため、頬をつねって席につかせる →体罰
宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた。 →体罰
学習課題や清掃活動を課す。→OK
殴りかかろうとする生徒を、押さえつけて制止させる。→OK
などなど。
個人的には、こういう具体的な基準を設けることはナンセンスじゃないかなあ、と感じます。
身体的な苦痛や負荷を与えられたとき、
それを不当な暴力と感じるか、正当な指導と受け止めるかは内面的な話しです。
例えばある生徒が大事な試合の日に寝坊して、遅刻して会場にやってきたとき、
仲間に対して申し訳なくて恥ずかしくて、どうしたらいいか分からず先生のところに行くと、
先生が「馬鹿野郎!」と一喝して大きなビンタをはる。
張り倒された生徒に先生は「早く着替えろ!」と怒鳴りつけ、後はもう遅刻のことには触れず、試合に突入していく。
それを見た仲間は、誰もその生徒を責めようとは考えません。
生徒は遅刻した分精一杯がんばろうと、大急ぎで着替え、仲間のもとに走っていきます。
このとき、生徒は先生のビンタによって救われているかも知れません。
もし私がその生徒なら、先生に感謝したと思います。
ビンタ一発によって、その数秒の行為で仲間や先生から「許し」を得て、気持ちを切り替えて試合に臨めたのです。
このとき、先生が体罰を用いず、
「今日は大事な試合なのに、お前は遅刻をして、みんなに迷惑をかけて、ウォーミングアップもできず・・・」
などなど口頭で説教をしたとしたらどうでしょう。
もし私がその生徒なら、意気消沈して試合どころではなくなる気がします。
逆に、先生が自分に対して愛情がなく、悪意を持っていると感じるなら、
それが軽く頭をはたく程度の行為でも、たたくフリだけでも、生徒は傷つき、精神的に大きな苦痛を感じるはずです。
叩くから悪い、口頭で注意しているからよい、というものではない気がします。
それを、外から見て「ここからここまでは暴力、ここまではOK」と線引きしようとするのは本質を見失っているやり方のような気がします。
(訴訟が起きた際に、円滑に裁判を進めるのには役立つかも知れませんが)
こういう基準を念頭に置きながら、慎重に指導にあたる現場の先生方は本当に大変だと思います。
指導するときはそのときそのときが勝負ですから、
「あれ、これ体罰になるんじゃね?」
「こういう言い方したら、後で問題になるんじゃね?」
なんていちいち考えている間に、もう動くべきタイミングは逸してしまいます。
教室でナイフを振り回した生徒を、後で殴った校長先生が辞めたそうですが、
私だったら教室でナイフを出した生徒を見た瞬間に殴り倒し、
とりあげたナイフで自分の手を切って
「お前はこうやって人を殺そうとしたんだ」
と血を見せるぐらいのことはすると思います。
問答無用で悪いことは悪いのです。
どんな事情があったとしてもそれはいけないことだ、ということを分からせるためには、
その瞬間に反射的なスピードでそれを知らせる必要があります。
そうでなければ「問答無用」ではなくなります。
教室で刃物を振り回す行為がいけないことだというのは、
とくとくと説明して分からせるようなことではないのです。
予想通りかなり長文になってまいりました。
この話題についてはまた日を改めて、引き続き述べてみたいと思います。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
☆毎月第3日曜日午後3時~ 社会人文章講座好評実施中!(1回のみの参加もできます)
2013年02月05日
苦手なことに立ち向かう

こんにちは。
豆腐や納豆が大好きなのに、プリン体が気になるので
大豆は控えめにしている春風館の望月です。
静岡では私立高校の入試がいよいよ明日からとなりました。
今回受験する人のほとんどが、「生まれて初めての受験」を経験することになります。
緊張したり不安を感じたりすることもあると思いますが、それも含めて大切な体験です。
体調を整えて、当日に臨んで下さい。
みなさんの健闘を期待しています!!
ところで今回のような高校入試では、
筆記試験がキライな人も決められた教科のテストを受けなければなりませんし、
初対面の人と話すのが苦手な人も面接官と話すことを強要されます。
こういう画一的な受験方法というのにはいろんな意見があるのかも知れませんが、
私としては、特に中学生くらいまではこういった「苦手なことも強制的にやらされる」経験は大切なのではないかと考えています。
自分自身、苦手なことがたくさんある人間なのでよく分かるのですが、
自分が苦手だと感じていることを、自分から積極的にやろうという人はなかなかいません。
やらなければ苦手なままですから、ひょっとしたらやれば得意になっていたはずのことも、
やらずに終わってしまう可能性があります。
だからこそ義務教育があり、すべての人が、
いろんなジャンルの基本的な勉強にくまなく触れられる環境が用意されているのだと思います。
教科やジャンルによって手を抜くのではなく、何にでも一生懸命取り組んでみる。
そうして大人になっていくうちにだんだんと、自分の得意不得意や向き不向きが見えてくる。
小中学生のうちから苦手だ嫌いだと言って逃げまくっていたら、
本当の自分の才能など見つけられずに終わってしまう気がします。
「苦手なことを無理してやらなくていいんだよ」
「もっと自分らしく、自分のよいところを伸ばしていけばいいんだよ」
しばらくの間、子供の教育に関してこういう風潮がはやっていた時期もあったように思います。
しかし、その一見優しそうな「ゆるし」は、子供のいろんな成長のチャンスを取り上げてしまうことだったのかも知れません。
小中学生のみなさん
いろんな勉強をする中で、「これは苦手だなあ」と感じたときは、
目をそむけてやめてしまうのではなく、
苦手だからこそじっくり勉強してみるようにして下さい。
もし他の人より時間がかかっても、焦ったり、恥ずかしく思ったりする必要はありません。
苦手なことを逃げずにやろうとする経験は、
(そのときの結果として他の人よりも成績が悪かったとしても)
みなさんを強く、賢く成長させていくのです。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
豆腐や納豆が大好きなのに、プリン体が気になるので
大豆は控えめにしている春風館の望月です。
静岡では私立高校の入試がいよいよ明日からとなりました。
今回受験する人のほとんどが、「生まれて初めての受験」を経験することになります。
緊張したり不安を感じたりすることもあると思いますが、それも含めて大切な体験です。
体調を整えて、当日に臨んで下さい。
みなさんの健闘を期待しています!!
ところで今回のような高校入試では、
筆記試験がキライな人も決められた教科のテストを受けなければなりませんし、
初対面の人と話すのが苦手な人も面接官と話すことを強要されます。
こういう画一的な受験方法というのにはいろんな意見があるのかも知れませんが、
私としては、特に中学生くらいまではこういった「苦手なことも強制的にやらされる」経験は大切なのではないかと考えています。
自分自身、苦手なことがたくさんある人間なのでよく分かるのですが、
自分が苦手だと感じていることを、自分から積極的にやろうという人はなかなかいません。
やらなければ苦手なままですから、ひょっとしたらやれば得意になっていたはずのことも、
やらずに終わってしまう可能性があります。
だからこそ義務教育があり、すべての人が、
いろんなジャンルの基本的な勉強にくまなく触れられる環境が用意されているのだと思います。
教科やジャンルによって手を抜くのではなく、何にでも一生懸命取り組んでみる。
そうして大人になっていくうちにだんだんと、自分の得意不得意や向き不向きが見えてくる。
小中学生のうちから苦手だ嫌いだと言って逃げまくっていたら、
本当の自分の才能など見つけられずに終わってしまう気がします。
「苦手なことを無理してやらなくていいんだよ」
「もっと自分らしく、自分のよいところを伸ばしていけばいいんだよ」
しばらくの間、子供の教育に関してこういう風潮がはやっていた時期もあったように思います。
しかし、その一見優しそうな「ゆるし」は、子供のいろんな成長のチャンスを取り上げてしまうことだったのかも知れません。
小中学生のみなさん
いろんな勉強をする中で、「これは苦手だなあ」と感じたときは、
目をそむけてやめてしまうのではなく、
苦手だからこそじっくり勉強してみるようにして下さい。
もし他の人より時間がかかっても、焦ったり、恥ずかしく思ったりする必要はありません。
苦手なことを逃げずにやろうとする経験は、
(そのときの結果として他の人よりも成績が悪かったとしても)
みなさんを強く、賢く成長させていくのです。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
2012年11月12日
私立単願の意義

こんにちは。
あまりにも運動不足だと思い解消する手段を考えつつ、
けっきょくまだ運動不足な春風館の望月です。
早いもので今年も11月半ば。
中3生は12月初めに学力調査テストを受けた後、
学校の先生と相談して志望校を決めていく時期にきています。
公立高校をどこにしようか迷っている人はもうしばらく考えることができますが、
私立高校については冬休みに入るまでには受験する高校を決める必要があります。
私立単願の人も、公立と私立を併願する人も、よく考えて自分に合った志望校を決定して欲しいものです。
ところで静岡の場合、公立高校は当日の入試次第で合否が変わってきますが、
私立高校は学校の成績が足りていれば(つまり先生が大丈夫だと判断して願書を出してもらえれば)、
あとは試験を受けさえすればほぼ合格するということで知られています。
このシステムのおかげで、中学生は公立との併願にせよ私立単願にせよ、
少なくとも私立高校には合格できることが分かっているので、
浪人等を心配せずに受験勉強に取り組めるわけです。
ただ、ここで懸念されるのは「私立単願に決めた生徒が、それ以降勉強をしなくなってしまうのでは?」という点です。
例年、公立高校を受験する生徒はどんなに成績がよくても当日次第という感覚があるので、
不安にかられつつ3月の入試まで必死に勉強に取り組みます。
一方、私立単願に決めてしまった生徒はもう受かることは分かっているので、
公立も受ける生徒に比べて格段にモチベーションが下がり、勉強を怠けてしまう傾向にあるのです。
これは実は恐ろしいことで、私立単願の大きな落とし穴とも言えるかも知れません。
中学生は1~2年の頃と、3年生になってからでは格段に勉強量が変わるのが普通で、
なかには1年のうちから勤勉にやる子もいるかも知れませんが、
一般的には「受験があるから」勉強に身を入れるのであり、
春から夏からと言いながら、結局のところ志望校が決まる中3の冬以降になって、
やっと本気で勉強に取り組むようになる生徒が多いのだと思います。
したがって、中学3年間のうちで、
本来12月~2月くらいの数カ月というのは、一番勉強をして学力を上げる時期だと考えられます。
1~2年生のうちは分からないこともスルーして、テキトーにやってきた生徒も、
この時期に1年内容からしっかり復習して、
受験までにはいちおう中学生としての学力を身につけて、
そして高校での勉強に臨んでいく。
そういうもののような気がします。
私立単願の人がもう大丈夫だと安心して勉強を怠けてしまったとしたら、
一番学力が上がる大切な数カ月を捨ててしまうことになります。
私立単願にした人は、公立併願者よりもむしろ強靭な心を持って、
甘えることなく自分の勉強を続けていくべきなのだと思います。
交流させていただいている神戸の新風館さんでは、
「合格はゴールなんかじゃない」ということが以前から言われているようです。
まさしくその通りだと思います。
どこの学校に行くか、合格するかということは本人にとって大切な通過点ではありますが、
実際には入った後からどうがんばるかが大切で、そのあとも人生はずっと続いていきます。
高校が決まったからと安心して今の勉強を怠けることのリスクはあまりにも大きいのです。
私立単願に決めた人はこの冬以降、
「入試当日に点数をとるための勉強」を強いられる公立併願の人に比べると、
マイペースに自分のレベルに合わせて、本当の実力を上げるための勉強をすることができます。
例えば英語が苦手が人は、1年内容から戻って最初からゆっくり勉強し直す余裕さえ生まれるのです。
それは非常に恵まれたことだと思います。
私立単願に決めた人は、安易に考えて勉強を怠けてしまうのではなく、
より学費のかかる私立へ進学させてもらえる環境にも感謝して、
きちんと勉強をして誠意をもって入試に臨んで下さい。
これからの数カ月で身につけた学力は、高校進学後の自分を大きく助けることになるはずです。
☆今月の社会人向け文章講座は、11月18日(日)の午後3時~5時を予定しています。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
あまりにも運動不足だと思い解消する手段を考えつつ、
けっきょくまだ運動不足な春風館の望月です。
早いもので今年も11月半ば。
中3生は12月初めに学力調査テストを受けた後、
学校の先生と相談して志望校を決めていく時期にきています。
公立高校をどこにしようか迷っている人はもうしばらく考えることができますが、
私立高校については冬休みに入るまでには受験する高校を決める必要があります。
私立単願の人も、公立と私立を併願する人も、よく考えて自分に合った志望校を決定して欲しいものです。
ところで静岡の場合、公立高校は当日の入試次第で合否が変わってきますが、
私立高校は学校の成績が足りていれば(つまり先生が大丈夫だと判断して願書を出してもらえれば)、
あとは試験を受けさえすればほぼ合格するということで知られています。
このシステムのおかげで、中学生は公立との併願にせよ私立単願にせよ、
少なくとも私立高校には合格できることが分かっているので、
浪人等を心配せずに受験勉強に取り組めるわけです。
ただ、ここで懸念されるのは「私立単願に決めた生徒が、それ以降勉強をしなくなってしまうのでは?」という点です。
例年、公立高校を受験する生徒はどんなに成績がよくても当日次第という感覚があるので、
不安にかられつつ3月の入試まで必死に勉強に取り組みます。
一方、私立単願に決めてしまった生徒はもう受かることは分かっているので、
公立も受ける生徒に比べて格段にモチベーションが下がり、勉強を怠けてしまう傾向にあるのです。
これは実は恐ろしいことで、私立単願の大きな落とし穴とも言えるかも知れません。
中学生は1~2年の頃と、3年生になってからでは格段に勉強量が変わるのが普通で、
なかには1年のうちから勤勉にやる子もいるかも知れませんが、
一般的には「受験があるから」勉強に身を入れるのであり、
春から夏からと言いながら、結局のところ志望校が決まる中3の冬以降になって、
やっと本気で勉強に取り組むようになる生徒が多いのだと思います。
したがって、中学3年間のうちで、
本来12月~2月くらいの数カ月というのは、一番勉強をして学力を上げる時期だと考えられます。
1~2年生のうちは分からないこともスルーして、テキトーにやってきた生徒も、
この時期に1年内容からしっかり復習して、
受験までにはいちおう中学生としての学力を身につけて、
そして高校での勉強に臨んでいく。
そういうもののような気がします。
私立単願の人がもう大丈夫だと安心して勉強を怠けてしまったとしたら、
一番学力が上がる大切な数カ月を捨ててしまうことになります。
私立単願にした人は、公立併願者よりもむしろ強靭な心を持って、
甘えることなく自分の勉強を続けていくべきなのだと思います。
交流させていただいている神戸の新風館さんでは、
「合格はゴールなんかじゃない」ということが以前から言われているようです。
まさしくその通りだと思います。
どこの学校に行くか、合格するかということは本人にとって大切な通過点ではありますが、
実際には入った後からどうがんばるかが大切で、そのあとも人生はずっと続いていきます。
高校が決まったからと安心して今の勉強を怠けることのリスクはあまりにも大きいのです。
私立単願に決めた人はこの冬以降、
「入試当日に点数をとるための勉強」を強いられる公立併願の人に比べると、
マイペースに自分のレベルに合わせて、本当の実力を上げるための勉強をすることができます。
例えば英語が苦手が人は、1年内容から戻って最初からゆっくり勉強し直す余裕さえ生まれるのです。
それは非常に恵まれたことだと思います。
私立単願に決めた人は、安易に考えて勉強を怠けてしまうのではなく、
より学費のかかる私立へ進学させてもらえる環境にも感謝して、
きちんと勉強をして誠意をもって入試に臨んで下さい。
これからの数カ月で身につけた学力は、高校進学後の自分を大きく助けることになるはずです。
☆今月の社会人向け文章講座は、11月18日(日)の午後3時~5時を予定しています。
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
2012年06月06日
教科書改訂でガンバレ中2

こんにちは。
TVアニメ「とっとこハム太郎」を一度も観たことがない癖に、
なぜか喜んでとっとこハム太郎のツイートをフォローしている春風館の望月です。
さて、本年度から中学生の教科書が全面改訂され、
ボリュームはざっと1.5倍、内容もかなり難しくなりました。
昔はこれが当たり前だった、とは言っても急に変えられた方はけっこう大変なわけで、
当事者の公立中学生や現場の先生方は、いろいろ苦労をされていることと思います。
どの学年の子も大変なのですが、
とりあえず、気持ち的なものも含めると一番大変なのが2年生かなあ、という気がしています。
例えば英語の教科書では、「新しい教科書では1年で習っているはずの単語」が、
もう覚えているものとしてしらっと登場します。
学校の授業にそって新出単語を覚えるものと思っていた子は戸惑いもあるでしょう。
1年生なら、最初から新しい教科書なので「そういうものだ」と思って授業が受けられますし、
3年生なら、もう受験生ですから細かいことは気にせず1年内容から総復習する時期に来ています。
2年生は受験生のような意識はまだなく、
中学生としての勉強を去年までの教科書で慣れてしまっていますから、
ちょっとやりにくいところもありそうです。
ただでさえ、中2からは英語も数学も理科も内容が難しくなり、
挫折してしまう人が多く出てきてしまうところ。
少しハンデにはなりますが、現中2生には教科書変更に惑わされず、
しっかり勉強をして授業内容についていって欲しいものです。
とりあえず最初の定期テストを乗り切れば、新しい教科書にも慣れてしまうことでしょう。
がんばって下さい!
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!
TVアニメ「とっとこハム太郎」を一度も観たことがない癖に、
なぜか喜んでとっとこハム太郎のツイートをフォローしている春風館の望月です。
さて、本年度から中学生の教科書が全面改訂され、
ボリュームはざっと1.5倍、内容もかなり難しくなりました。
昔はこれが当たり前だった、とは言っても急に変えられた方はけっこう大変なわけで、
当事者の公立中学生や現場の先生方は、いろいろ苦労をされていることと思います。
どの学年の子も大変なのですが、
とりあえず、気持ち的なものも含めると一番大変なのが2年生かなあ、という気がしています。
例えば英語の教科書では、「新しい教科書では1年で習っているはずの単語」が、
もう覚えているものとしてしらっと登場します。
学校の授業にそって新出単語を覚えるものと思っていた子は戸惑いもあるでしょう。
1年生なら、最初から新しい教科書なので「そういうものだ」と思って授業が受けられますし、
3年生なら、もう受験生ですから細かいことは気にせず1年内容から総復習する時期に来ています。
2年生は受験生のような意識はまだなく、
中学生としての勉強を去年までの教科書で慣れてしまっていますから、
ちょっとやりにくいところもありそうです。
ただでさえ、中2からは英語も数学も理科も内容が難しくなり、
挫折してしまう人が多く出てきてしまうところ。
少しハンデにはなりますが、現中2生には教科書変更に惑わされず、
しっかり勉強をして授業内容についていって欲しいものです。
とりあえず最初の定期テストを乗り切れば、新しい教科書にも慣れてしまうことでしょう。
がんばって下さい!
小中学生の学習指導・社会人文章講座に関するお問い合わせは
TEL:054-201-9801
juku@shunpukan.net
春風館(望月)まで
☆中学生・小学生通常コースの無料体験実施中!